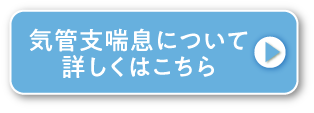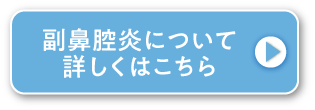痰がからむ原因とは?痰の症状や上手な出し方とあわせて解説
- クリニックブログ
痰がからむ原因とは?痰の症状や上手な出し方とあわせて解説

痰の症状や上手な出し方と
あわせて解説

咳や痰が続くと、呼吸器の病気、最近では新型コロナウイルス感染症の心配をしてしまう方も多いのではないでしょうか。
痰についてはマイナスイメージをお持ちの方が多いかもしれません。
しかし、痰は体にとって重要な役割を果たしているのです。
一方で、病気のサインであることも否定できません。
この記事では、痰とは何か、痰が出る原因、痰の上手な出し方などについて解説します。
病院受診の目安にも触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。
痰とは何か
痰とは、気道から出る分泌物のことです。
体内に入った異物を体の外に排出しようとする働きがあるなど、ウイルスや細菌に対しての体の防御反応ともいえるでしょう。
ここでは、痰ができる原因、痰を体外に出した方がいい理由、痰と関係が深い病気について解説いたします。
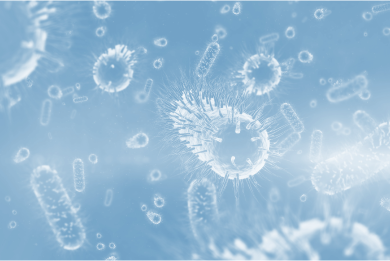
痰には、感染予防のために活動した白血球の残骸や、大気中のちり、喫煙者であればたばこのすすなど、さまざまなものが含まれています。
乾燥するとウイルスに感染しやすくなってしまうため、気道は基本的に粘液でうるおった状態となっています。しかし、異物が入ったり、細菌やウイルスに感染したりすると、分泌物の量や粘りが増して、痰となるのです。

痰を体外に出した方が良い理由は、主に2つあります。
1つは呼吸との関係です。
痰が溜まった状態が続いて気道が狭くなると、呼吸に支障をきたすことがあります。
また、体内は高温多湿の環境となっているため、体内の痰は細菌が繁殖する場となってしまうおそれがあります。
もう1つの理由としては、感染予防が挙げられます。体内は高温多湿の環境となっているため、体内の痰で細菌が繁殖してしまうおそれがあります。
そして、繁殖した細菌が感染症を引き起こす可能性もゼロではありません。呼吸のしやすさと感染予防を考えると、痰は出す方が望ましいといえるでしょう。
痰が絡むことに関係している病気の一例としては、以下が挙げられます。
肺炎の一種である誤嚥性肺炎は、唾液や食べ物が、食道ではなく誤って気管に入ってしまうことが原因となっている肺炎です。
特に、飲み込む力が弱くなった高齢者に多い病気といわれています。
- ● 気管支喘息
- ● 肺炎
- ● 慢性閉塞性肺疾患
- ● 気管支拡張症
- ● 肺結核
- ● 肺がん
- ● 誤嚥性肺炎
高齢者は、のどの力が弱くなり、飲み込む力(嚥下機能)も低下しているため、痰が溜まりやすくなっています。
本来なら咳をすることで痰を出しますが、高齢者の場合、肺の力も低下しているため咳そのものが困難です。
そのため、スムーズに痰を出せなくなってしまっているのです。
水分をとって、痰をやわらかくすることも大切ですが、水やお茶などさらさらした液体は、むせやすいので、少しとろみをつけるとよいでしょう。

また、加湿器を利用したり、洗濯物を室内に干したりして加湿することも痰を出しやすくする方法の1つです。赤ちゃんの場合、自分で上手に痰を出すことがまだできません。
そのため、痰が絡まって息が苦しくなったり、痰を詰まらせて嘔吐したりする危険があります。
発熱時などは、痰が出やすくなるように、いつもより多めに水分を与えると良いでしょう。
痰の色と症状
一般的に、健康な人の痰は無色透明です。
痰に色がついている場合は、ウイルス及び細菌感染症、もしくは肺がんや気管支喘息といった呼吸器疾患の可能性が考えられます。
痰の量が増える、痰の色が濃くなってきているという場合は、早めに呼吸器専門の医療機関を受診しましょう。
透明な痰や白い痰の原因として考えられるのは、以下のとおりです。
この中でも気管支喘息の場合は、透明かつ粘り気の強い痰が出ることが特徴です。
痰の色が黄色くなる原因としては、風邪、細菌及びウイルス感染などが挙げられます。
感染から体を守るために、血液成分の1つである白血球(好中球)が活発に働き、好中球の残骸と痰が混ざることで、好中球に含まれる酵素の色調により黄色くなるのです。
また、痰が緑色になることもあります。
主な原因は、黄色の痰と同じくウイルスや細菌の感染です。
それ以外の原因としては、以下のものがあげられます。
痰の色が濃くなったり量が増えたりした場合は、早めに呼吸器専門の医療機関を受診しましょう。
茶色の痰は、呼吸器疾患が原因であることが多く、肺炎や肺結核、肺がんなどが疑われます。
赤色の痰は、風邪をひいたときなど、痰を無理に出そうとしてのどの奥が切れてしまった際に出ることがあります。
新型コロナウイルスに感染したことで激しい咳が続き、それが原因で痰に血が混じる場合もあります。
痰の上手な出し方
痰を上手に出すのは、呼吸のしやすさや感染症予防の点でも大切なことです。
これから紹介する方法は、呼吸リハビリとも呼ばれるもので、中には理学療法士などリハビリの専門家による指導を受けた方がよいものもあります。
ハッフィングとは、自分一人で行える痰の排出方法です。
まずは深呼吸を3~5回程度繰り返します。
その後、胸を手で押さえながら、強く息を吐きましょう。
これで痰が上がってくるようであれば、2~3回咳をして、痰を出します。
胸や喉の奥に痰が張り付いているように感じる場合は、このハッフィングがおすすめです。
痰が残っているようであれば、もう1度この動作を行いましょう。
ただし、何度も行うと、のどを痛める可能性があるので、5~10分程度にとどめるようにしてください。


体位排痰法とは、ハッフィング同様に自分一人で痰を排出するための手法の一つです。
肺の上部や背中側など、痰が溜まっている場所に応じて、それぞれ排出しやすい体位で寝ることで、重力の力により痰を出しやすくします。
痰が溜まっている部分が自分では把握しにくい場合は、医師や看護師、理学療法士の指導を受けましょう。
痰が溜まっている部位によって、姿勢が異なるので注意してください。
3つ目は呼吸介助法と呼ばれるもので、医療関係者やご家族が行います。
主な呼吸介助法には、痰がある部位を気道に向かって圧迫する「スクイージング」、痰がある部分を軽くたたいて痰の移動を促す「クラッピング」などがあります。
まとめ
痰は体を感染から守る大切なものですが、同時に病気のサインでもあります。
痰がからんで苦しい、痰が黄色くなったり血が混じったりしているというように、
いつもと違う状況が続くようであれば、早めに呼吸器専門の医療機関を受診しましょう。
MYメディカルクリニックには、呼吸器内科外来がございます。
痰のことでお悩みの方は、ぜひ一度ご来院ください。

監修:MYメディカルクリニック渋谷 非常勤医
笹倉 渉Dr. Sasakura Wataru
-
資格麻酔科標榜医 / 日本医師会認定産業医
-
専門麻酔・救急・内科 / 外科全般
-
資格藤田保健衛生大学医学部 卒業
公立昭和病院
東京慈恵会医科大学附属病院麻酔科 助教
北部地区医師会病院麻酔科 科長
2016 年 MY メディカルクリニック 医師