
検査で分かる病気
脳の検査


脳ドック
- この検査でわかる病気
-
- 脳動脈瘤
- 頸部頸動脈狭窄症
- 検査説明
- 脳ドックは、自覚症状の出にくい脳血管の動脈硬化や脳動脈瘤をはじめとした脳疾患リスクの早期発見と、その発症の予防及び専門医療機関への早期紹介を主な目的としています。
- 脳ドックをお勧めする方
-
- 喫煙や飲酒される方
- 頭痛がある方
- ストレス過多の方
- 高血圧、肥満、脂質異常傾向の方
- 糖尿病や心疾患の方
- ご家族に脳血管疾患の病歴がある方
- 40歳以上で一度も脳ドックを受診したことがない方
アルツハイマーリスク検査
- この検査でわかる病気
-
- アルツハイマー病
- 検査説明
- 高性能MRIを使用し、加齢や飲酒などによって進行する脳の萎縮度等を調べる検査です。アルツハイマーの進行を遅らせるためには、早期の治療が大切です。アルツハイマーは、いつも通っている道で迷う、物忘れがひどくなるといった初期症状が出ますので、この時点で本人か家族が気付き受診することが大切です。
- アルツハイマーリスク検査を
お勧めする方 -
男性の方が多くなりやすい
2009年に発表した結果では、若年性認知症患者は、調査時点で4万人弱、男性の方が女性よりも多く、発病年齢は平均で約51歳と言われています。若年性認知症は、脳血管性型とアルツハイマー型の2つが圧倒的に多く見られます。とはいえ、罹患者は少数ですが、高齢者でも見られる前頭側頭葉型やレビー小体型、事故などで脳に損傷を受けたために起こる頭部外傷後遺症や、多量のアルコールを飲む事で脳が委縮する、アルコール性の認知症なども見られます。
眼の検査


眼底・眼圧検査
- この検査でわかる病気
-
- 緑内障
- 白内障
- 網膜剥離
- 検査説明
-
眼底
動脈硬化、高血圧、糖尿病による眼の合併症や緑内障・白内障の有無などの状態を検査します。眼底の血管、網膜、視神経を調べる検査です。網膜剥離や眼底出血、緑内障、黄班部変性などの目の病気を調べることができます。
眼圧
眼にごく少量の空気を吹き付けて、眼の柔らかさを測定します。眼の中に含まれる水分量によって、眼の柔らかさ(眼圧)が決まります。眼圧が高いと緑内障の疑いがあります。日本人の失明の原因のなかで2位に位置づけられる病気が緑内障です。自覚症状がほとんどないままに進行する緑内障では、病気発見の手がかりは検査しかありません。
- 眼底・眼圧検査をお勧めする方
- 40歳を過ぎたら、定期的に眼底検査を受けるようにしましょう。血縁者に緑内障にかかった人がいる場合には特に早めに受けることをオススメします。
色覚検査
- この検査でわかる病気
-
- 色覚異常
- 検査説明
- 色覚検査表を使用して色覚異常を調べる検査です。雇用者側から色覚異常の有無についての報告要求がある場合に、入社時の健康診断の検査項目に含まれるケースや職業により必要な検査となります。
胃の検査

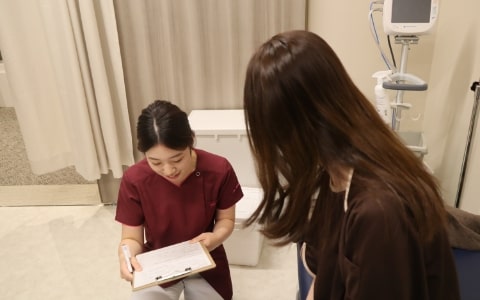
ペプシノゲン検査
- この検査でわかる病気
-
- 胃がん
- 萎縮性胃炎
- 検査説明
-
血液を数cc採取するだけの非常に簡便な検査です。血液中のペプシノーゲンの割合を調べると、胃粘膜の萎縮の広がりとその程度、胃液の分泌機能、胃粘膜の炎症の有無が分かるほか、胃がんのスクリーニング検査として有用であることが明らかとなり、注目されています。
「血液検査による胃がん検診」とも呼ばれています。この検査だけで、胃がんと判定することはできないので胃X線検査や上部消化管内視鏡検査などの画像診断との併用が基本になります。
- ペプシノゲン検査をお勧めする方
-
40歳以上が対象の検査ですが、被曝等のリスクがないことからさらに若年や妊娠の可能性のある女性にも適用できます。
ヘリコバクターピロリ抗体検査
- この検査でわかる病気
-
- 胃がん
- 慢性胃炎
- 胃潰瘍
- 検査説明
- 血液検査でピロリ菌感染の有無を調べる検査です。ピロリ菌は胃の中に好んで住みつき、胃の壁を傷つける細菌です。日本人の50%以上がピロリ菌に感染しており、中でも50代以降では保持者の割合が70%以上に達します。ピロリ菌の感染が胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの原因になることは確実で、胃がんの発生にも深く関連しています。実に胃がん患者の80%以上が感染者であるとの報告もされています。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の経験がある方や再発をくりかえす方など、消化性潰瘍と診断された方、また胃がん家系でご心配な方や、なんとなく胃の具合がいつも悪い方などは検査をお勧めします。
尿素呼気試験
- この検査でわかる病気
-
- 胃がん
- 慢性胃炎
- 胃潰瘍
- 検査説明
- 検査薬を服用し、服用前後の呼気でヘリコバクターピロリ菌感染の有無を調べる検査です。胃粘膜全体を検査するので、診断が正確です。除菌療法の治癒判定には最も優れています。胃粘膜の検査なので空腹時に検査を受けてください。
- 尿素呼気試験のオススメ点
-
- 内視鏡検査を受けなくて良いので、全く苦痛がありません。
- 試験薬は自然界にも微量に存在するので安全です。
- 検査時間は20分、測定時間は5.5分と短時間で終了しますから、30分程で検査結果を知ることが出来ます。
※この検査は、活動性の胃潰瘍や十二指腸潰瘍が胃カメラ検査または胃透視にて証明された場合、及びその除菌治療後の治癒判定の場合のみが保険診療の対象となります。繰り返す胃・十二指腸潰瘍で困っている方、慢性胃炎の種々の症状でお困りの方、胃がん家系の方などでご心配の方は、ご相談ください。
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
- この検査でわかる病気
-
- 胃がん
- 慢性胃炎
- 胃潰瘍
- 検査説明
- 上部消化管とは食道・胃・十二指腸を指し、口または鼻から内視鏡を挿入し、これらの部位を一連の検査で観察します。
- 胃カメラのココがスゴイ
-
上部消化管X線造影検査で食道や胃、十二指腸に疑わしい影が見つかった際、その部分の粘膜を直接観察できるため、病変の大きさや形、色、出血の有無までがはっきりとわかり、確定診断に役立ちます。また、がんが疑われるときには、内視鏡先端部の装置を使って疑わしい組織部を採取し、生検(組織細胞診)を行なえば確実に診断できます。
5mm以下の非常に早期のがんもこの内視鏡検査で発見が可能です。
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)
- この検査でわかる病気
-
- 大腸がん
- 大腸ポリープ
- クローン病
- 潰瘍性大腸炎
- 大腸憩室症
- 虚血性腸炎
- 検査説明
-
内視鏡を肛門から挿入し全大腸と小腸の一部を観察する検査です。
大腸がんは40代から徐々に罹患者数が増え、60代に最も多いがんです。2018年の国立研究開発法人国立がん研究センターの調査では、がん罹患者数の総数は大腸がんが1位でした。大腸内視鏡検査は、大腸内の腫瘤や潰瘍等リアルタイムに目視で確認できる非常に有用な検査です。また、がんが疑われる場合にはその場で組織を採取し生検をおこなうことで確実に診断することも可能です。
循環器の検査


心不全リスク検査(採血)
- 心不全を引き起こす心臓病
-
- 虚血性心疾患(虚血性心不全)
- 狭心症
- 心筋梗塞
- 心臓弁膜症
- 僧帽弁閉鎖不全症
- 不整脈(頻脈・徐脈)
- 心筋炎
- 心筋症
- 心アミロイドーシス
- 心房中隔欠症
- 心室中隔欠損症など
- 検査説明
- 血液検査で心筋バイオマーカーのNT-proBNPを調べ、心臓の状態を検査します。心不全とは「病名」ではなく「状態」を指す言葉です。心不全をきたす原因は1つではありません。あらゆる心臓病や心臓に負担をかける病気などが心不全の原因になり、複数の原因が関与している場合もあります。
- 原因
- 過労/喫煙/風邪などの感染症/塩分や水分のとりすぎ/長時間や高温の入浴/飲酒/過度の運動(適度な運動は必要)/睡眠不足/過食による肥満/ストレス
- 心不全リスク検査(採血)を
お勧めする方 -
- 動悸や息切れがする
- 疲れやすい
- 顔色が悪い
- 咳、痰、呼吸困難、息切れ(仰向けに寝ると苦しい)
- 手足が冷たい
- 尿量の減少
心電図検査
- この検査でわかる病気
-
- 不整脈
- 心肥大
- 心筋虚血
- 心房中隔欠損症
- 心筋梗塞
- 拡張型心筋症
- 心臓偏位
- 心臓弁膜症
- 狭心症
- 電解質失調など
- 検査説明
-
心臓の筋肉が全身に血液を循環させるために拡張と収縮を繰り返すとき、微弱な活動電流が発生します。その変化を波形として記録し、その乱れから病気の兆候を読み取ろうとするのが心電図検査です。心臓がリズミカルに動いているかどうかがわかりますから、心臓のリズムが乱れる「不整脈」の診断には欠かせません。
「心筋梗塞」や「狭心症発作」のときには、心臓の筋肉(心筋)の電気的活動にも異常が生じるので、心電図にも異常が出てきます。さらに、なんらかの心臓疾患のために心筋に障害が起きている場合も異常心電図が認められます。このように心電図は心臓の検査の中で最も基本的なものです。息切れや、めまい、動悸、胸痛、失神といった症状が出た場合は検査をしましょう。
血管年齢検査
- この検査でわかる病気
-
- 動脈硬化
- 高血圧症
- 糖尿病など
- 検査説明
- 脈拍のような周期的で律動的な動きのことを「脈動」と呼んでいますが、血液も脈動しながら血管内を流れています。その速さや四肢の血圧の差を測り、血管の硬さと血管の詰まり具合を測定するのが、血圧脈波測定検査です。わかりやすく言えば、いわゆる「血管年齢」を調べる検査のことです。手と足の血圧の比較や脈波の伝わり方を調べることで、動脈硬化の程度を数値として表したものです。
この検査を行うことにより動脈硬化(血管の老化など)の程度や早期血管障害を検出することができます。肥満体の方、喫煙者、運動不足気味の方、心臓病や脳卒中の家族歴のある方などもオススメです。
呼吸器の検査


喀痰細胞診検査
- この検査でわかる病気
-
- 肺がんなど
- 検査説明
- 痰を採取して、その中にどのような病的な成分が含まれているかを顕微鏡で観察する検査で、呼吸器の病気を診断するためには不可欠なものとなっています。特に喫煙指数の高い人や血痰の見られる人などを対象に、胸部X線検査と合わせて実施されています。喀痰細胞診の最大のメリットは、肺の入り口に近い「肺門部」のがんを発見しやすいことです。
肺門部は、胸部X線検査では全体像が写りにくく、骨や血管などに隠れてがんが見逃されてしまうこともありますが、喀痰細胞診を併用することで発見率が上がります。特に、喫煙習慣のある男性に多い「扁平上皮がん」を発見しやすい検査です。また胸部X線検査と同様、検査が簡単というメリットもあります。
肺機能検査
- この検査でわかる病気
-
- 肺結核
- 肺線維症
- 拘束性肺機能障害
- 気管支喘息
- 気管支拡張症
- 閉塞性肺機能障害
- 混合性換気障害
- 肺気腫など
- 検査説明
- ぜんそく(喘息)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺疾患をはじめとする、呼吸器の病気が疑われるときや、その状態をみるときに行う検査です。息を吸ったり吐いたりして息を吸う力、吐く力、酸素を取り込む能力などを調べます。スパイロメータという機械を用いて、鼻から空気が漏れないようにクリップでつまみ、マウスピースという筒をくわえて、検査技師の指示に従って息を吸ったり吐いたりします。
- 肺機能検査をお勧めする方
-
- タバコの喫煙歴がある
- 一日に何度も咳が出る
- 一日に何度も痰が出る
- 通勤時、労作時に息切れする
- 40歳以上である
肺CT検査
- この検査でわかる病気
-
- 肺がん
- 肺結核
- 肺炎
- 肺気腫
- 気胸
- 胸部大動脈瘤
- 肺動静脈瘻
- 心臓疾患
- 検査説明
- 男女ともに罹患数・死亡数の多い肺がんですが、早期発見できれば開胸せずに治療することが可能になってきました。胸部X線検査では隠れて見えづらい部分も、マルチスライスCTではミリ単位の病変を抽出できるのでより的確な診断ができます。肺がんは高齢者だけでなく若年者も罹患する可能性があるのでCTによる定期健診をお勧めします。
- 肺CT検査をお勧めする方
-
- 本人や身近なかたが喫煙者の方
- 咳・痰が気になる方
- 胸痛・動悸・息切れが気になる方
- ご家族に呼吸器官の癌に罹患した方がいる方
- 頭痛・易疲労感・食欲不振・体重減少などの症状がある方
内分泌の検査


甲状腺ホルモン検査・超音波検査
- 検査説明
-
採血検査:甲状腺ホルモンのTSH・FT3・FT4を血液検査で測定します。
超音波検査:甲状腺を超音波で調べる検査です。甲状腺ホルモンバランスの乱れは男性でもありますが、女性のほうが比較的多いです。過労、出産後、精神的なストレスなどからホルモンバランスが乱れると言われています。
- 甲状腺ホルモン検査・超音波検査を
お勧めする方 -
- 甲状腺腫大
- 発汗過多
- 眼球突出
- 手の震え
- 動悸
- 生理不順
- 体重減少
※症状は患者様それぞれに違いがあり、症状が見られない方もおられます。肌荒れ、イライラ、脱力感、疲労感、抜け毛、むくみなど、身体の変化が気になる方はまずは簡単な採血検査から受けられるのがオススメです。
泌尿器の検査


前立腺MRI
- この検査でわかる病気
-
- 前立腺がんなど
- 検査説明
- この検査を行うことにより、バイオプシー(針生検)では特に見逃しがちであった移行部のがんなどを、高感度で発見できるようになりました。MRI拡散強調画像の特徴はバイオプシー(針生検)に比べ、浸襲性がきわめて低く、且つがん病巣を高感度に検出できることです。
- 前立腺MRIをお勧めする方
-
- 放射線の被ばくがない
- どの部位でも検査することができる
- 横断、縦断などどんな断面でも画像を得ることができる
- 断面画像だけでなく、血管だけを画像化することもできる
- 病変部と正常組織のコントラストがはっきりしていて見やすい
婦人科の検査
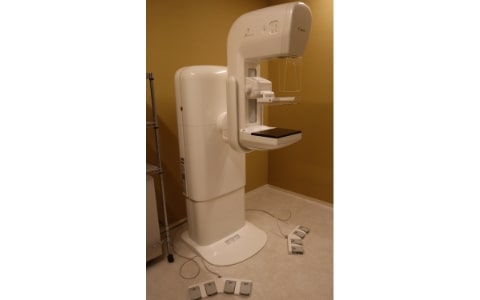

子宮頸部細胞診
- この検査でわかる病気
-
- 子宮頸部異形成
- 子宮頸がんなど
- 検査説明
- 子宮頸部細胞診は子宮の入り口をブラシや綿棒で擦り、細胞を採取してがん細胞や、がんになりかけている細胞(異形細胞)の有無を調べる検査です。ほとんど痛みのない簡単な検査で検査自体の所要時間は2~3分程度です。子宮頸がんは性交渉によりHPV(ヒトパピローマウイルス)に感染することで発症します。HPVによって細胞に異常を引き起こし、がん化していくため当院ではHPVの感染の有無を調べる検査も行っております。
経膣超音波
- この検査でわかる病気
-
- 子宮筋腫
- 子宮内膜ポリープ
- 卵巣腫瘍など
- 検査説明
- 経膣超音波専用の細い棒状のプローブ(探触子)を膣内に挿入し、子宮や卵巣の状態を観察します。画像で診ることが可能なため、がん健診だけではわからない子宮筋腫や子宮内膜ポリープ、卵巣嚢腫等の異常所見を見つけることができます。
子宮・卵巣MRI
- この検査でわかる病気
-
- 子宮筋腫
- 子宮内膜症
- 子宮体がん
- 卵巣がんなど
- 検査説明
- 子宮や卵巣などの骨盤内臓器は心拍動や呼吸運動に影響を受けにくい位置にあるので婦人科疾患の診断にMRI検査は最適です。MRI検査は、X線被曝がないため繰り返しの検査が安心して受けられるというメリットがあります。婦人科診察(内診や細胞診)と併せて受けられることをおすすめします。
軟部組織(子宮、卵巣、筋肉、腸、肝臓などの内臓類)のコントラスト分解能が非常に高いため、子宮筋腫の大きさ、位置、その内部の性状、子宮腺筋症と子宮筋腫の違い、卵巣腫瘍の内部に貯留している液体の性状などの分解能が非常に高いため婦人科疾患の診断はCTよりも優れており、腫瘍性病変の評価には欠くことができない検査法となっています。
- 子宮・卵巣MRIをお勧めする方
-
- 辛い生理痛で毎回鎮痛剤飲んでいるが、痛みが治まらない
- 生理痛が年々酷くなってきている
- 月経血の量がかなり多い(夜用ナプキンでも1時間で取り替えなければいけない、など)
- 生理以外のときも下腹部痛がある
- 性交時、腰が引けるほどの痛みを感じる
- 生理のたびに鎮痛剤の量が増えてきている
- 生理中に吐き気や嘔吐することがある
- 月経血の中にレバー状の血の塊が出ることがある
- 排便時に肛門の奥に痛みを感じる
- 下腹部にしこりがある
乳房超音波検査
- この検査でわかる病気
-
- 乳がんなど
- 検査説明
- 乳がんをはじめとした乳房の異常の有無を超音波画像で調べます。無症状のうちに乳がん検診を受診した人では、乳がんが早期に発見される可能性が高く、その段階で適切な治療をすれば、良好な経過が期待できます。針を刺したり、放射線や薬を使わないので、身体への負担は軽く、乳腺密度の高い人や若い人への検査に適しているといわれています。
感染症の検査
HIV検査(採血)
- この検査でわかる病気
-
- ヒト免疫不全ウイルス
- エイズって何?
- HIVがTリンパ球やマクロファージ(CD4陽性細胞)などに感染した結果、これらの細胞の中でHIVが増殖します。このため、免疫に大切なこれらの細胞が体の中から徐々に減っていき、普段は感染しない病原体にも感染しやすくなり、さまざまな病気を発症します。この病気の状態をエイズ(後天性免疫不全症候群)と言います。
- HIVはどうやって感染するの?
-
HIVに感染すると、HIVは血液、精液、膣分泌液、母乳などに多く分泌されます。唾液、涙、尿などの体液では他のヒトに感染させるだけのウイルス量は分泌されていません。感染は、粘膜(腸管、膣、口腔内など)および血管に達するような皮膚の傷(針刺し事故等)からであり、傷のない皮膚からは感染しません。そのため、主な感染経路は「性的感染」、「血液感染」、「母子感染」となっています。
性的感染
HIV感染は、性行為による感染が最も多いです。主として、女性は膣粘膜から、男性は性交によって生じる亀頭部分(粘膜)の細かい傷から、精液、膣分泌液に含まれるHIVが侵入することで感染します。コンドームを用いない性行為をしたり、HIVに感染したかも・・・と不安に思った時には、いつでも検査を受けてみてください。HIV感染はHIV検査を受けないと見つけることはできません。
各院の診療時間・アクセスは
下記よりご確認ください。






